2024年はどうなる!?住宅業界の展望
2024.01.08
2024年の住宅業界はどのような年になるのか、大変気になるところです。
新型コロナが5類感染症となり少し落ち着きを取り戻した感じはありますが、住宅業界には避けては通れない課題が多々あります。
そこで本記事では2024年の住宅業界の予想をまとめてみました。
\ 関連記事 /
目次
住宅業界の現状

住宅業界の現状を以下の事柄別に解説します。
- 人材不足
- 新設住宅着工戸数
人材不足
住宅業界の現状として人材不足が続いています。
人材不足の原因として、以下のことがあげられます。
- 若手の離職問題
- ベテランの引退
- 労働人口の減少
若手の離職問題
建設業界における新人社員の離職率は平均で38%とされており、これは多くの若者がこの業界を去っていることを示しています。
建設業界はかつて3K(過酷、不潔、危険)と称され、さらに最近では新3K(労働強度が高い、厳格な管理、長時間労働)ともいわれています。
これが労働者にとって働きやすい環境でないとされる大きな要因となっています。
ベテランの引退
建設業界においては、55歳以上の労働者が全体の30%を超える一方で、29歳以下の若手労働者は約10%程度にとどまっています。
このような状況は、経験豊富なベテラン労働者が圧倒的に多いことを示しています。
しかし、これらのベテラン労働者の多くが10年以内に退職する見込みであり、それによって人手不足が慢性的な問題となっています。
さらに、これらのベテラン労働者の中には多くの資格を持っている人も多く、彼らの退職により、専門的なスキルを持った労働力が減少することが予想されます。
労働人口の減少
労働力人口の縮小は、少子高齢化の影響で加速しており、将来的には増加する可能性がほぼないとされています。
これに対処するために、政府はいくつかの対策を進めています。
労働環境を改善し、働く人が業界を去らないように取り組むことが一つの戦略です。
加えて、女性が職場でより活躍することを支援し、労働力人口の確保につなげる試みも行われています。
さらに、外国からの労働者を積極的に雇用することで、人手不足を緩和する方針も採られている地域があります。
人口全体の減少は避けられないものの、これらの対策によって労働力人口の減少を抑制する試みが進められています。
また、労働力が限られている状況でも、IT技術の導入などによって生産性を向上させ、同等あるいはそれ以上の成果を出すための手段も検討されています。
新設住宅着工戸数
2023年の新設住宅着工戸数は国土交通省によると、69,561戸となっており、今後も市場は縮小すると予想できます。
株式会社野村総合研究所の発表によると、新設住宅着工戸数の推移は2030年度は70万戸、2040年度は49万戸と減少する見込みとなっています。
日本では将来的な人口の減少が見込まれており、これに伴って新しい住宅を建設する需要も低下すると予測されています。
結果として、限られた顧客層を巡って激しい競争が繰り広げられる可能性が高まっています。
2024年の住宅業界の予想

2024年住宅業界予想①:コロナ禍で住宅に対しての意識は健在
2022年はコロナ禍の影響でステイホームを強制されたことで、2024年は住環境に関心をもった人が増え住宅ブームとまでいわれています。
2024年も人々の住宅への関心は続くと予想されます。
テレワークを導入する企業もさらに増加すると想定されています。
家中の時間が増えれば、さらによい環境で過ごしたいと思う人は増え、新築やリフォームの需要は高くなるかもしれません。
2024年住宅業界予想②:高まる顧客の知識
最近では住宅関連の情報をX(旧Twitter)やFacebookだけでなく、YouTubeでもよく見るようになりました。
建物の構造に関してや、住宅ローンの説明など詳しく説明しているチャンネルもあり、非常に勉強になります。
そのため、事前に情報を集めて知識が高い顧客が多くなっているので、営業をする側の能力や知識も顧客以上に高めなければなりません。
2024年住宅業界予想③:ZEHの提案の増加
脱炭素に向けて注目されているZEHは、2024年は大きなトレンドになりそうです。
ZEHは「Zero Energy House(ゼロエネルギーハウス)」の略で、国が2030年までには省エネ基準をZEHに引き上げると発表しています。
その目標に向け、2022年から「住宅の脱炭素施策」として動いています。
また、国土交通省・経済産業省・環境省の3省の連携での補助もあり、ZEHの推進に力を入れていく方針です。
そのことから、2024年はZEHの提案をするハウスメーカーや工務店が増えていくと予想されます。
>>経済産業省 資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」
2024年住宅業界予想④:材料の高騰
アメリカや中国で木材需要が増加したことから今後、ますます材料の高騰が予想されます。
アメリカでは、ロックダウンの緩和と低金利政策の組み合わせが住宅建設の需要を刺激し、結果として住宅の着工数が増加しました。
一方で、中国における木材の需要増加が、木材の国際市場における供給不足を引き起こし、これが木材価格の上昇につながっています。
日本においては、建築用木材の約70%が輸入に依存しているため、この国際的な木材価格の上昇が日本の建設業界に大きな影響を及ぼしています。
さらに、輸入木材の高騰に対処するために国産材への関心が高まっているが、これが木材市場全体の価格を押し上げる要因となっているのです。
2024年住宅業界予想⑤:リフォーム市場の拡大
新築住宅の着工数が減少する一方で、リフォーム市場は拡大の道を辿ると見込まれています。
矢野経済研究所の調査によれば、リフォーム市場は2030年までゆるやかな増加が予想されています。
これを受けて、新築住宅に特化していた住宅メーカーや工務店がリフォーム市場に進出する動きが見られるかもしれません。
しかし、市場に参加する企業が増えることで競争が激しさを増すため、成長市場であっても競合他社との差別化が不可欠となります。
2024年の住宅業界にとっての不安材料

2024年住宅業界の不安材料①:資材ショック
コロナショックによるステイホームの影響で、アメリカを中心に住宅ブームがおきました。
そのため木材の需要が高まり、日本は資材の買い負けをし、供給制約や価格上昇によるウッドショックがおきたのです。
また、コロナ拡大でのロックダウンの影響で建材・設備工場のストップもあり、全体的に資材不足がおこり、その影響は2024年も続くと予想されています。
2024年住宅業界の不安材料②:オミクロン株で続くコロナショック
ワクチン接種率の向上で、一旦落ち着きをみせた新型コロナですが、新たに発生したオミクロン株により人々のコロナ禍の生活は終わりが見えない状況です。
そのため、住宅に興味があっても人々の動きは良くないと予想されています。
2024年は昨年よりも働き方を見直し、見込み客をどう獲得するか考えなければなりません。
続くコロナ禍。2024年の住宅業界の働き方はどうなる?
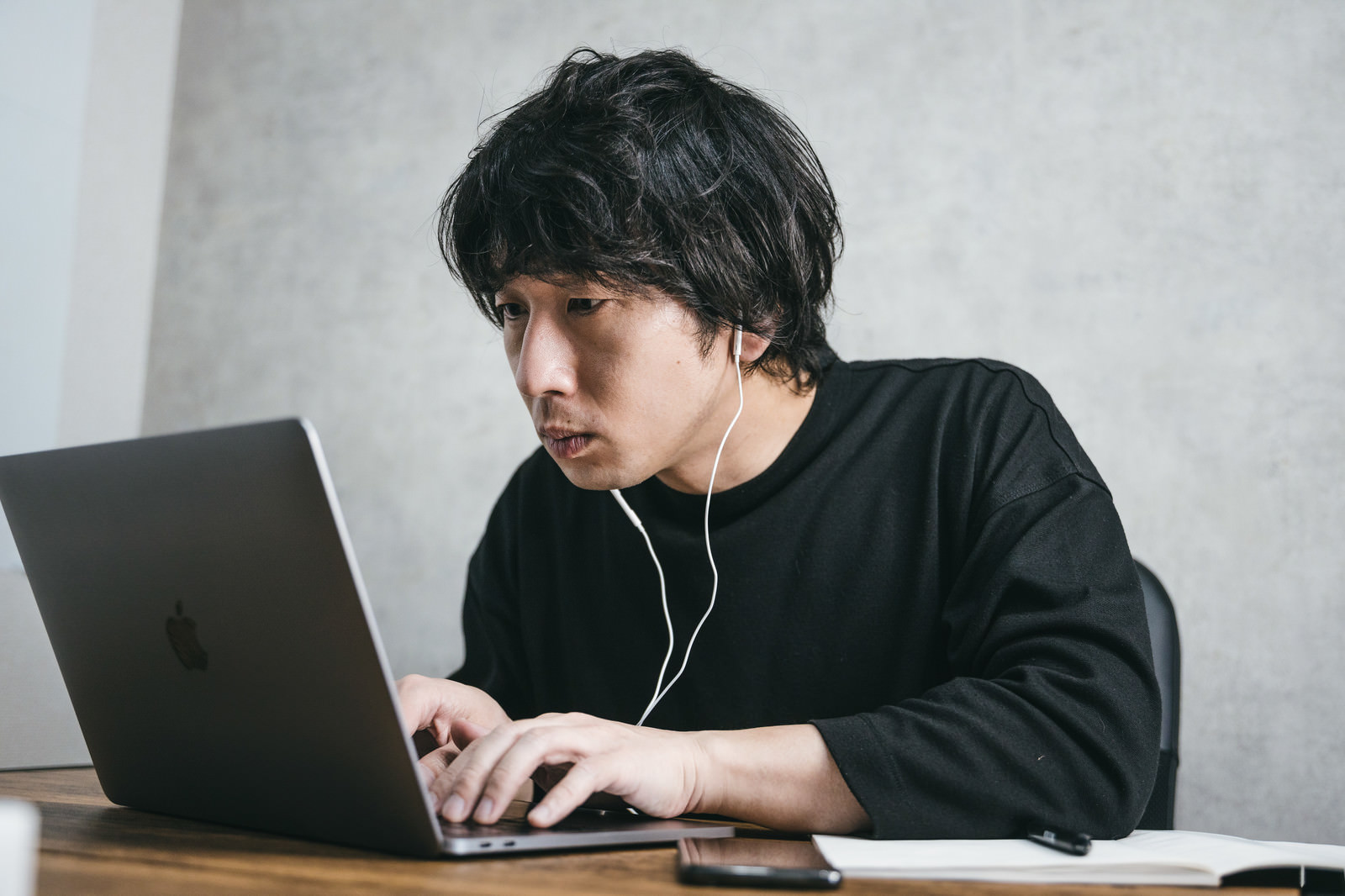
2024年住宅業界の働き方①:テレワークの継続
昨年はコロナの影響でテレワークを導入した企業が増加しました。
さらに、新たに猛威をふるうオミクロン株やインフルエンザの影響で2024年もテレワークは必要となりそうです。
そのため、制度化する企業も増えテレワークの定着がますます進むと予想されます。
2024年住宅業界の働き方②:オンライン商談
テレワークが続くのであれば、顧客との商談もリモート商談がメインとなるスタイルに変化する可能性が高いです。
PCやスマートフォンがあれば、Zoomなどのアプリを使用することでリモート商談は可能です。
一部の住宅会社ではすでにリモート商談が進んでいますが、今後はオンラインで顧客とやり取りをする会社が増えるでしょう。
デジタル化の導入で業務を変革

テレワークとオンライン商談を進めるために必要となってくるのはデジタル化です。
社内とは違い、オンラインでのやり取りがメインとなるので紙ベースで仕事をすることは大幅に減ります。
また、デジタル化をする事で経費の削減にも貢献できるので、是非進めたい変革です。
2024年の住宅業界はSNSを活用した見込み客の獲得

SNS広告の増加で飽和状態に
近年、SNS広告を利用したハウスメーカー・工務店は急激に増え、YouTube、Instagramなどの動画広告もよく見るようになりました。
その背景として、コロナ禍で集客方法を見直し、新たな戦略としてSNSを取り入れた企業が増加しています。
おそらく、今後も増加傾向にあるので、他社との差別化を図る戦略が必要となってくることでしょう。
例えば、メールマーケティングは住宅業界では活用されていないので、まだ住宅業界が手を出していない従来のマーケティングで差別化をはかるのも一つです。
オンラインセミナーで見込み客を
SNS広告が飽和状態になりつつある中、単に広告を出しただけでは顧客の獲得に繋がりません。
その先の戦略の一つにオンラインセミナーがあります。
これまでの集客では、個別で対面での相談であったり、会場を借りてセミナーを行うという形が主流でしたが、コロナ禍の今ではその形式は厳しくなっています。
そこでオンラインセミナーを取り入れ、見込み客を獲得する企業が増えていきます。
YouTube動画などによる情報発信
YouTubeなどの動画による情報を発信する企業も増えいます。
動画は情報量も多く、続けて発信することで会う前から顧客と信頼関係を構築できるというメリットがあります。
その反面、動画のクオリティーから企業のイメージダウンにも繋がる場合もあるので注意が必要です。
顧客の役に立つ情報の発信を続ければ、オンラインセミナーなどへの流入も見込める可能性もあることでしょう。
2024年に住宅業界が抱える課題
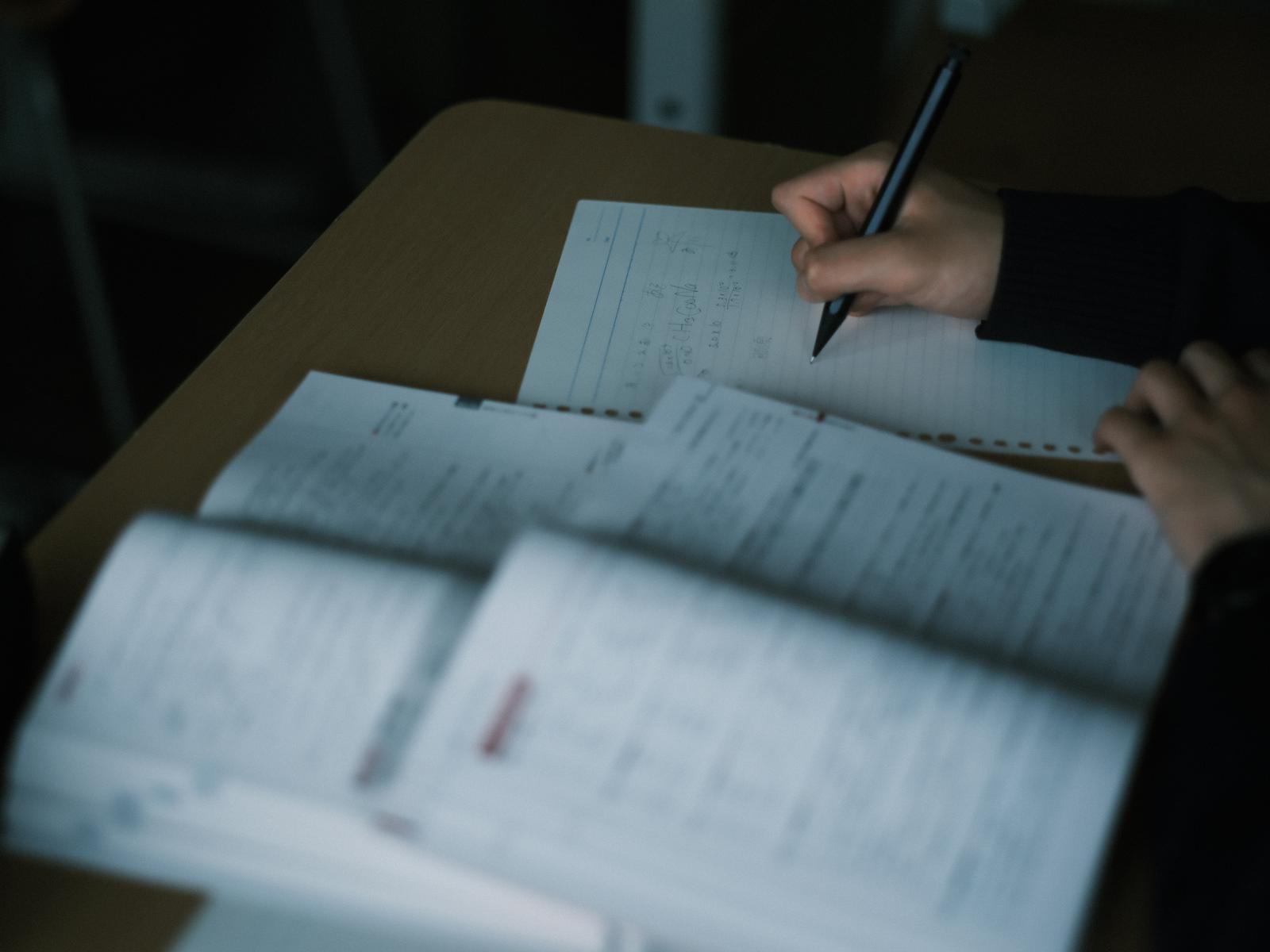
2024年の住宅業界の課題①:インボイス制度
インボイス制度は2023年10月から開始された制度で、簡単に説明をすると仕入税額控除を受けるには、仕入先や下請け業者から「適格請求書」を発行してもらう必要がある制度です。
さらに問題な点は、適格請求書の発行は課税事業者のみ発行が可能なことから、免税事業者の多い一人親方との取引をどうするのか考えなければなりません。
住宅業界は大工をはじめ職人不足であるため、この制度によって人手が足りない状況に陥りそうです。
2024年の住宅業界の課題②:DXレポートによる2025年の崖
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、ITを駆使した事業の変革のことを指します。
簡単に説明しますと、これからの時代には今までのシステムでは限界があるので、ITを駆使し新しいシステムで事業を変えていき、顧客に新しい価値を与えなくてならないということです。
2024年の崖とは、経済産業省が発表した「DXレポート」の結果の一つで、DXを取り入れない企業は2025年には事業機会を失い日本の経済に大きく影響を及ぼすという内容です。
このことからDXの導入は日本の企業の大きな課題となるのです。
- 関連記事:DXとは何のこと?住宅業界との関連性は?
2024年の住宅業界の課題③:若者の減少
人口の減少とともに若者が減っている日本。
住宅業界に限った問題ではないですが、若者の人口が減少すると産業の衰退を招くことになります。
さらに働き手も減り、特に職人の不足は住宅業界に大きな問題となってきます。
その一方で、高齢者の人口は増え、2035年には65歳以上の人口が三分の一になると予測されています。
住宅業界はとどまることのない若者の減少にどう対策をするかが、大きな課題となると思います。
まとめ【住宅業界は今後を見込んで対策が必要】
住宅業界にとって2024年は昨年と同等な景気と予測されています。
しかし、材木不足と資材不足、円安による物価高騰の問題もあるので先行きは不透明な感じもします。
また、インボイス制度をはじめ、様々な課題も多く、その課題に対して動いていく必要があると思います。
この状況下は、チャンスです。
他社よりも先に新しいものを取り入れて、自社の独自性を生み出し、差別化していくことで売上を大きく上げることも、今しかできません。
新型コロナによる影響は少なくなっているとはいえ、不安な時期は続きますが、未来を見据えた対策をすることが2024年の大きなテーマです。
デキる会社の経営を
カタチにしました
リフォーム統合管理システム「SAKSAK」はできる会社の経営管理をカタチにしたシステムです。SAKSAKを使うことで、次のような悩みを解消いただけます。
- 粗利管理ができていない
- 請求書の確認に時間と手間がかかる
- 会社として顧客管理ができていない
- 見積書作成は営業担当者の負担が大きい
- 入金遅延や未入金・額の相違が多い など
意外と、知られてはいませんがリフォーム業界20年という実績があるシステムです。SAKSAKを使って、利益率が5%アップした会社もあります。また、SAKSAKとともに上場した会社もあります。
次は、SAKSAKがあなたの会社をお手伝いする番です。まずは、どのようなシステムか、ご覧ください。
導入事例集もありますので、こちらもご参考ください。
建築業、リフォーム業向けにすぐに使えるエクセル4種類のテンプレート(御見積書・工事請負契約書・工事台帳・工程表)を無料でプレゼントしております。

\ 関連記事 /
- 関連キーワード:
- 業界動向


