現場監督ってどんな仕事?|信頼される現場監督になるコツについて解説
2023.07.11
工事現場で作業員やスタッフの中心となって陣頭指揮をとる現場監督。
建設現場で作業を行う上で必要不可欠な現場監督とは、一体どのような仕事なのでしょうか。
この記事では、現場監督の業務内容にスポットを当て、キャリアアップに活かせる資格や、信頼される現場監督になるためのコツについて解説します。
現場監督と施工管理者

建設現場を統括する現場監督と施工管理者は、同義とされることも多く、その役割についてはあまり知られていません。
現場で全体を指揮する現場監督と施工管理者の概要や仕事内容、それぞれの特徴について解説します。
現場監督とは|資格は必要?
現場監督とは、建設現場において建築工事や土木工事、電気工事など、あらゆる作業を指揮する管理者のことです。
建設業者は、元請けや下請けなど現場の規模に関係なく、すべての建設現場に技術者を配置する必要があります。
技術者には、主任技術者と管理技術者がいます。
- 主任技術者
⇒すべての建設現場に配置 - 管理技術者
⇒特定建設許可を要する建設現場に配置
現場監督は、必ずしも資格が必要なわけではありません。
しかし、将来的に主任技術者や管理技術者としてスキルアップを望むなら、国家資格である施工管理技士の資格を取得することがおすすめです。
施工管理者とは
施工管理者は、建設現場で働く作業員の業務を監督し、全体を指揮する役割を担います。
具体的には、工期内に工事を完了するための工程を組んだり、資材や作業人員等の調整を行ったりします。
現場監督と施工管理者の違いについて
現場監督は、建設現場において管理を行う業務が、主な仕事です。
施工管理者は、施工管理技士などの資格保有者を指す場合が多く、現場管理と事務作業の両方を担います。
資格を有している施工管理者は、事務作業の印象が強く、現場監督は現場での作業イメージが強いことから、事務作業を行う人を施工管理者、現場作業を行う人を現場監督と表現する場合もあります。
実際には、施工管理者が現場監督を兼任している場合が多くみられます。
持っていると活かせる資格
現場監督が、現場管理をするうえで、活かせる資格には、施工管理技士の資格があります。
施工管理技士の資格は、仕事内容や現場によって次のような種類があります。
- 建築施工管理技士
⇒一般戸建て住宅やマンションなど、建設工事の管理を行う技術者の資格 - 電気工事施工管理技士
⇒受変電設備や照明、送電線など、電気設備の管理を行う技術者の資格 - 土木施工管理技士
⇒道路や橋、トンネルなどインフラ設備を中心とした土木工事の管理を行う技術者の資格 - 管工事施工管理技士
⇒空調設備やガス配管など、設備工事の管理を行う技術者の資格 - 造園施工管理技士
⇒公園や植栽などの造園工事、道路や屋上への緑化作業の管理を行う技術者の資格 - 建設機械施工技士
⇒多くの建設機械を使用する現場において、指導や管理を行う技術者の資格 - 電気通信工事管理技士
⇒インターネットや電話など、情報通信設備に関わる電気通信工事の管理を行う技術者の資格
施工管理技士の資格には、1級と2級があります。
1級を取得すると、管理技術者として大規模な建設現場の管理を行うことができます。
2級を取得した場合は、主任技術者として中小規模の現場管理に就くことができます。
現場監督の業務内容
現場監督の主な業務内容として「工程管理」「安全管理」「原価管理」「品質管理」があげられます。
- 工程管理
⇒工期内での施工完了を目指し、効率的に工程スケジュールを管理します - 安全管理
⇒作業員の安全確保のため、事故やトラブルを想定した環境整備や安全行動を行います - 原価管理
⇒予算内で工事を完了するため、人員管理や工程を改善します - 品質管理
⇒設計図や仕様書通りの品質に仕上がっているか確認する作業を行います
現場の安全を守り、快適な環境を整備する安全管理も大切な業務のひとつです。
安全対策として次の活動を進めます。
- KY活動(危険予知活動)
- 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
- ヒヤリハット運動
上記のような安全活動は、習慣化してしまうことが多く、形式的になりがちです。
現場での安全かつ災害ゼロへの取り組みは、業務の向上にも直結します。
現場監督だけでなく、働く作業員への安全に対する意識付けをすることが重要です。
関連記事:工程管理システムとは?導入目的やメリット、選び方について解説
信頼される現場監督になるコツ

多くの業種が集まる建設現場では、現場を取りまとめて、スムーズに工事を進めるために信頼される現場監督になることが必要不可欠です。
信頼される現場監督になるための、心構えやスキルについて解説します。
リーダーシップのある現場監督
現場監督は、工程管理や原価管理、品質管理、安全管理などの管理能力が求められます。
現場を管理し円滑に進めるため、作業員への適切な指示やアドバイスを行えるリーダーシップが必要です。
現場での各工事に積極的に携わり、熱意と統率力のある現場監督は、作業員からの信頼度も高く、頼れる存在となります。
行動がスピーディで決断力と統率力がある現場監督
工事を進めていく中で、発生するトラブルを的確に判断し、作業員が迷わずに施工を行えるようにするため、現場監督にはスピーディな決断力が求められます。
作業員を統率するために、ときには指導をしたり、注意喚起を施したりすることも大切です。
たとえ作業員の方が経験豊富であっても、現場監督として的確な判断は不可欠です。
知識を持っている現場監督
現場や工事、建築について学び、知識を深めることが重要です。
信頼される現場監督になるためには、自信を持つことも大事なポイントです。頼りがいのない監督では、信頼を得ることができません。
現場監督としての判断力が自信に満ちたものになるように、建設に関する知識を十分に身に付けておきましょう。
コミュニケーション力がある監督
現場監督は、作業員への態度が傲慢であったり、命令的であったりしてはいけません。
年上で経験豊富な作業員も多いなかで、現場を取りまとめてスムーズに作業を行う要となるスキルがコミュニケーション力です。
経験の浅い現場監督が、信頼されるには時間を要します。そのためにも丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。
作業の説明を適切にしたり、わかりやすく指示を出したりするなど、作業員が快適に仕事に当たれる環境を作ることが信頼される現場監督になるためのポイントです。
作業員のモチベーションを向上させ、高品質な仕事をしてもらうことは、現場監督としての勤めでもあります。
作業をスムーズに進める段取り力のある監督
現場で必要な材料が届いていない、あるいは、発注を間違えるなどのトラブルが頻発すると、信用を失うだけでなく工程に支障をきたします。
また、作業中の不具合を伝え聞いても、対応が遅くいつまでたっても改善しなければ信頼されることもなく相手にされなくなる可能性もあります。
信頼される現場監督になるためには、速やかに行動に移せる積極性と段取り力を磨く必要があります。
責任感のある監督
現場で働く作業員は、それぞれ良質な仕事を提供しますが、任せきりにするのは良くありません。
最後まで責任を持って現場を指揮することが大切です。
また、現場監督は時間厳守で仕事をすることが重要です。時間にルーズな監督だと信頼を得ることができません。
現場監督の一日

- 出勤(7時30分)
- 朝礼・KWミーティング(8時)
- 作業開始(8時30分)
- 現場巡回(8時30分〜11時30分)
- 打ち合わせ(11時30分〜12時)
- 昼休憩(12時〜13時)
- 昼礼(13時〜13時15分)
- 現場巡回(13時15分〜17時00分)
- 現場作業終了(17時)
- 事務作業(17時〜)
現場監督によって異なりますが、基本的にこのような一日を過ごします。
日中は現場確認や職人との打ち合わせがあるため、事務作業が17時以降になってしまうのがきびしいところです。
どうしたら日中に事務作業を進められるか考えながら、仕事をするのが大切です。
現場監督に向いている人の特徴
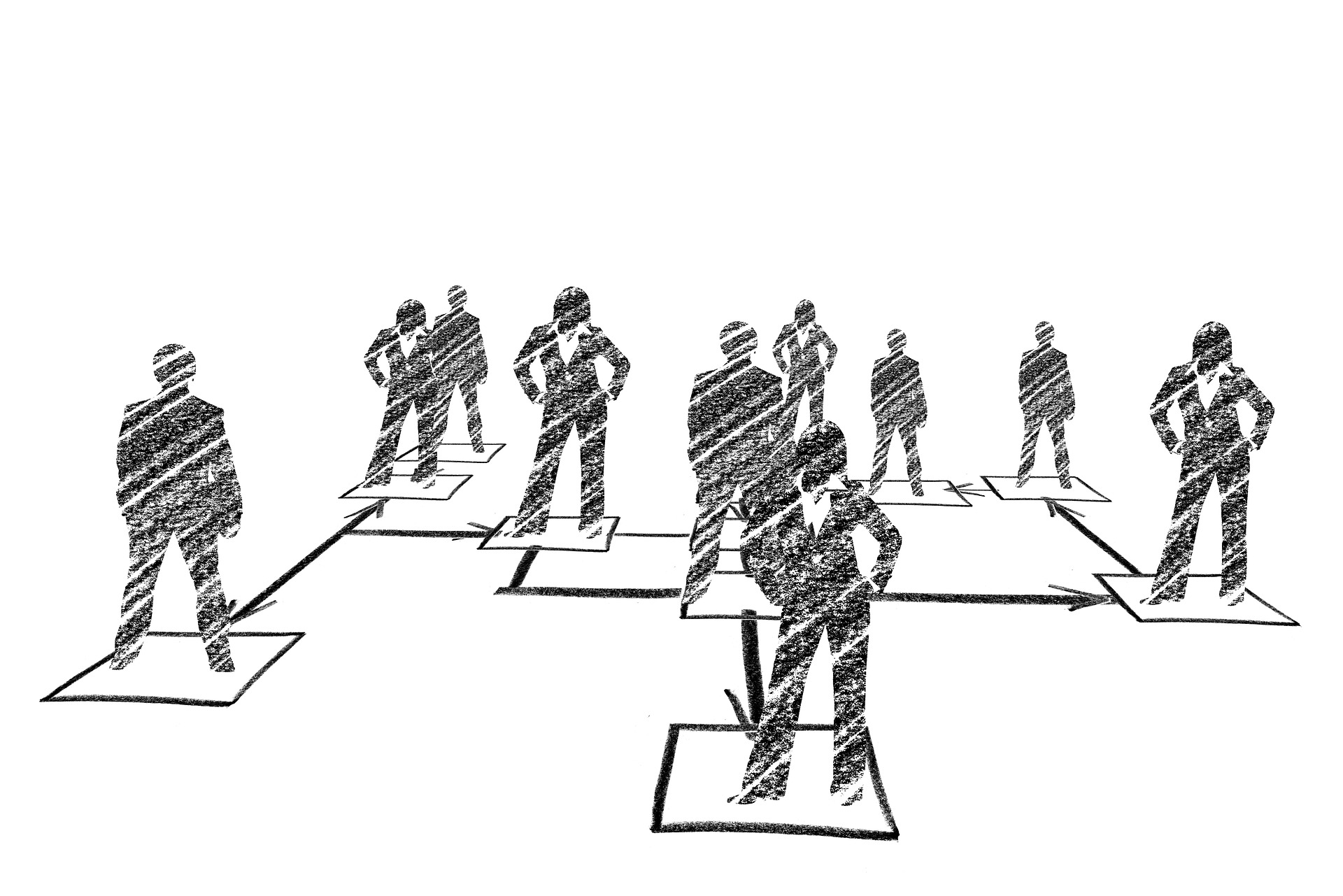
現場監督に向いている人の特徴は以下のとおりです。
- コミュニケーション能力がある人
- マルチタスク能力がある人
- 体育会系の人
コミュニケーション能力がある人
コミュニケーション能力があれば、職人や他の担当者とうまく打ち合わせができるため、仕事がスムーズにできます。
逆にコミュニケーション能力が乏しいと、知識が豊富でも仕事で能力を発揮できないでしょう。
もともとコミュニケーション能力がない人でも、現場にのまれれば気づいたら打ち合わせが得意になる場合があるため、問題ありません。
マルチタスク能力がある人
マルチタスク能力がある人は現場監督に向いています。
マルチタスクとは短時間で切り替えながら、複数の作業を行なっていくことです。
現場監督の仕事は複数の作業を同時進行にこなさなければなりません。
作業が重複すると、テンパってしまう方は思うように仕事が進まないため仕事ができないと思われてしまいます。
体育会系の人
現場監督は体育会系の人が向いています。
現場に携わる人、主に職人は基本的に体育会系の人です。
体育会系同士なら意気投合し、仕事が回ります。
逆になよなよしていると、コキに使われる場合が多いため仕事が進みません。
現場監督のやりがい

現場監督のやりがいは以下のとおりです。
- 建物が完成したとき
- 職人に感謝されたとき
- 図面とおりに現場が進んだとき
建物が完成したとき
建物が完成したときは現場監督をやってて良かったと思えるでしょう。
最初は何もない土地だったのに、竣工時には立派な建物が立っています。
工事中は辛いこともありますが、建物が完成した時には、それ以上に感情が動きます。
職人に感謝されたとき
職人に感謝されたときに現場監督のやりがいを感じます。
いつもは厳しい職人ですが、職人がやりやすいように段取りしたときに感謝されます。
職人からの感謝がモチベーションになり、仕事に熱が入ります。
図面とおりに現場が進んだとき
図面どおりに現場が進んだときにやりがいを感じます。
施工図を書いたときは実際の建物がないため、収まるかどうか不安です。
工事が進んでいき、施工図どおりに工事が進み、問題ないときに安心します。
この安心が次の工事にもつながるため、図面と現場の確認は大切です。
まとめ【信頼される現場監督になろう】
多くの作業員が働く建設現場で、現場監督が信頼を勝ち取るのに、特に重要なポイントは以下の3点。
- コミュニケーション力
- 統率力
- 決断力
逆に作業員が、監督から信頼されるためには、適切に物事を伝える力と正しくものを理解する力を備える必要があります。
現場監督と作業員がお互いを敬う気持ちを持って、より良い作業環境作りを目指し、建設業界のさらなる発展に貢献し、活動の場を広げていきましょう。
デキる会社の経営を
カタチにしました
リフォーム統合管理システム「SAKSAK」はできる会社の経営管理をカタチにしたシステムです。SAKSAKを使うことで、次のような悩みを解消いただけます。
- 粗利管理ができていない
- 請求書の確認に時間と手間がかかる
- 会社として顧客管理ができていない
- 見積書作成は営業担当者の負担が大きい
- 入金遅延や未入金・額の相違が多い など
意外と、知られてはいませんがリフォーム業界20年という実績があるシステムです。SAKSAKを使って、利益率が5%アップした会社もあります。また、SAKSAKとともに上場した会社もあります。
次は、SAKSAKがあなたの会社をお手伝いする番です。まずは、どのようなシステムか、ご覧ください。
導入事例集もありますので、こちらもご参考ください。
建築業、リフォーム業向けにすぐに使えるエクセル4種類のテンプレート(御見積書・工事請負契約書・工事台帳・工程表)を無料でプレゼントしております。

- 関連キーワード:
- 施工管理


