改正建築物省エネ法|建築会社がやらなければいけないこと
2022.04.05
2021年4月1日、改正建築物省エネ法が施行されました。
もととなった建築物省エネ法から約2年、義務が拡大し、建築会社にとっては業務が増える等、大変な思いをされているところもあるかもしれません。
しかし、この改正建築物省エネ法は、今後もより強く規制されていくはずのものです。
そもそも、建築物省エネ法とは何なのか。建築物省エネ法制定の背景と、改正建築物省エネ法に至る流れ、そして建築会社が「今後やらなければいけないこと」について今回は書いていきます。
目次
建築物省エネ法とは
建築物省エネ法とは、平成27年に公布された法律で、正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」です。
その建築物省エネ法が改正され、より厳しい基準になったものが「改正建築物省エネ法」(=現行法)であり、令和3年4月1日以降に建築確認申請を提出した物件から適用されています。
建築物省エネ法が施行された背景
当初の建築物省エネ法が公布、施行された背景は、パリ協定にあります。
このパリ協定とは、2015年にパリで行われた「国連気候変動枠組条約締約国会議」で合意された、温室効果ガス削減に関する国際的な取り決めのことです。
パリ協定は、1997年に採択された「京都議定書」という同様の目的で作られたものを修正、その範囲を拡大したようなものです。
先進国だけでなく途上国にも温室効果ガス排出量削減の努力を求めたものであり、「世界全体で温室効果ガス削減に取り組んでいこう」というもの。
日本の削減目標
日本はこのパリ協定で、「2030年時点で2013年度の水準から26.0%削減」という目標を設定。
ただ温室効果ガスを削減するだけではエネルギーに乏しい日本ではエネルギー不足に陥ることが濃厚であり、そのためエネルギーの効率化及び再生可能エネルギーの導入量を増加させるという対策が必須となりました。
住宅産業への影響
日本のエネルギー消費量の推移は、産業や運輸といったカテゴリーでは1990年代以降、減少しているにも関わらず、民生部門と言われる建築業界に関わる部門のみが年々上昇。
この民生部門は、住宅に住む人たちが使うエネルギー、事務所やビル、ホテル等の施設などで使われるエネルギーが含まれますが、この上昇している部分のテコ入れはその他の部門よりもより厳しく目標が定められる結果となりました。
それは、2030年度に向けて、家庭・業務における消費エネルギーを40%減らすという事です。
そのマイルストーンとして、こと住宅業界においては、2020年までにいわゆるZEH住宅を平均化しよう、という流れになっていったわけです。
建築物省エネ法の内容
そうして定められた、建築物省エネ法とは以下の通り。
下記の表にある現行省エネ法とは以前の省エネ法のことです。
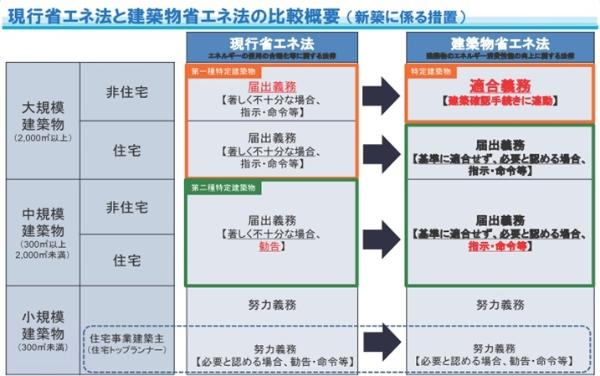
- 非住宅の大規模建築物(2,000㎡以上)については、適合義務が生じる
- 住宅の大規模建築物(2,000㎡以上)は基準に適合しない場合は指示・命令が発生する
- 非住宅、住宅問わず中規模建築物(300㎡以上2,000㎡未満)についても基準に適合しない場合は指示・命令が発生する
以前の省エネ法から、規制が厳しくなっている、といえると思います。
そして、この建築物省エネ法から改正されたものが、2021年4月から施行されています。
それが改正建築物省エネ法です。
改正建築物省エネ法の改正点
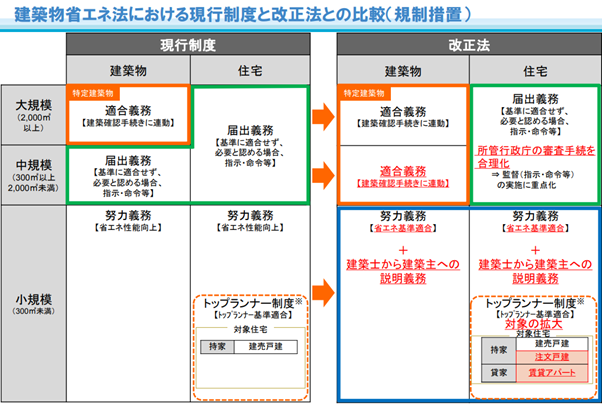
- 中規模(300㎡)以上の非住宅の建築物は、すべて適合義務が生じる
- 中規模(300㎡)以上の住宅の届出義務は変わらず、所管行政庁の審査手続きを合理化
- 非住宅、住宅問わず小規模建築物(300㎡以下)については、適合義務、届出義務等の規制は発生しないが、新たに説明義務が生じる
以上の通り、省エネ基準適合のための規制は厳しくなっていることが見て取れます。
なお、この他には、住宅トップランナー制度の対象が、
- 分譲戸建住宅を年間150戸以上供給する事業者
に加え、
- 注文戸建住宅を年間300戸以上供給する事業者
- 賃貸アパートを年間1,000戸以上供給する事業者
が追加となっており、これは対象を拡大したと言えます。
実際の業務
適合義務
省エネ適合性判定、建築確認、完了検査の手続きが必要です。
基準に適合していない場合、着工できず、また違反した場合には是正の命令・罰則があるので、しっかりと余裕をもって手続きをする必要があります。
届出義務
着工21日前までに所管行政庁への届出が必要です。
なお、住宅性能表示やBELS等、民間審査機関の審査結果を添付する場合は、着工3日前までの届出が可能です。
基準に適合しない場合、必要により所管行政庁が指示・命令をする場合があり、届出義務違反、命令違反には罰則もあります。
説明義務
こちらは行政での手続きではなく、建築士から建築主についての説明義務です。
書面で、省エネ基準への適否等の説明を行わなければなりません。
なお、これらの書面を建築士事務所に保存していなかった場合は、処分の対象となる場合があります。
今後の建築業界
この厳しい規制の流れは、まだまだ続きます。
経済産業省は、
- 2030年には新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保され、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が導入されていること
- 2050年にはストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保され、導入が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的となること
を掲げています。
そのための取り組みとして、
- 2025年度に住宅を含めた省エネ基準への適合義務化
- 遅くとも2030年までに省エネ基準をZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能に引き上げ・適合義務化
- 将来における設置義務化も選択肢の一つとしてあらゆる手段を検討し、太陽光発電設備の設置促進の取組を進める
としています。(ここでいう「ZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能」とは、再生可能エネルギーを除いた省エネ性能のこと)
※経済産業省HP、ニュースリリース「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の対策を取りまとめました」より抜粋
まとめ
ここまで見てきたように、2021年4月に施行された改正建築物省エネ法では、適合義務の対象拡大と説明義務が追加され、建築会社としては対応していかなければならないことがお分かりいただけたと思います。
しかし、それだけではなく、今後はこの適合義務の対象は更に拡大し、現在は非住宅の建築物のみに課せられている適合義務は、2025年度には住宅にも波及してくる予定です。
その時になってあれこれと調べてから始める、というと後手にまわってしまい、認可が下りず、工期の遅れが発生してしまう等の問題が起こってしまう可能性もあります。
幸い、経済産業省は中長期的な目標を出しているので、それにあわせ、先回りして様々なことに対応できるようにしておくことが肝要です。
デキる会社の経営を
カタチにしました
リフォーム統合管理システム「SAKSAK」はできる会社の経営管理をカタチにしたシステムです。SAKSAKを使うことで、次のような悩みを解消いただけます。
- 粗利管理ができていない
- 請求書の確認に時間と手間がかかる
- 会社として顧客管理ができていない
- 見積書作成は営業担当者の負担が大きい
- 入金遅延や未入金・額の相違が多い など
意外と、知られてはいませんがリフォーム業界20年という実績があるシステムです。SAKSAKを使って、利益率が5%アップした会社もあります。また、SAKSAKとともに上場した会社もあります。
次は、SAKSAKがあなたの会社をお手伝いする番です。まずは、どのようなシステムか、ご覧ください。
導入事例集もありますので、こちらもご参考ください。
建築業、リフォーム業向けにすぐに使えるエクセル4種類のテンプレート(御見積書・工事請負契約書・工事台帳・工程表)を無料でプレゼントしております。

- 関連キーワード:
- 法律関連


